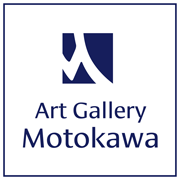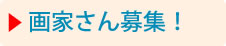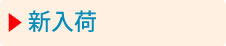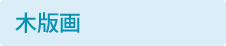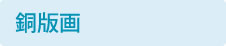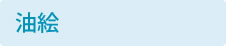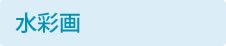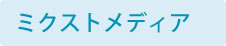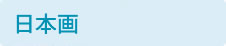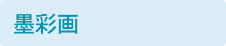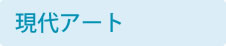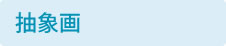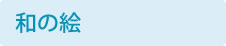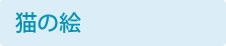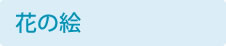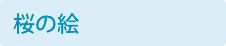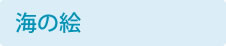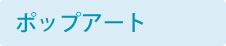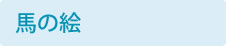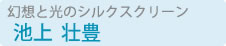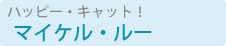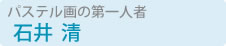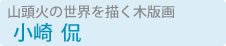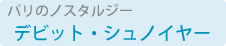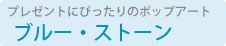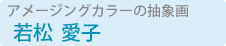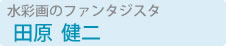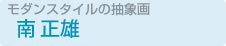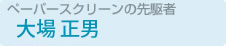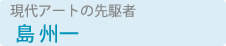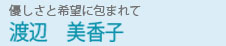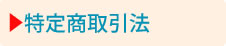造形作家・西村芳弘が焼き物で制作した造形作品を通販で販売しています。

絵画・版画の販売の専門店
株式会社アートギャラリーモトカワ
〒861-4101 熊本県熊本市南区近見6丁目1−57
営業時間10:00〜19:00
TEL 096-322-5222 水曜・定休日 info@motokawa.com

お問い合わせは
お気軽にお電話ください
096-322-5222

お問い合わせは
お気軽にお電話ください
096-322-5222

お問い合わせは
お気軽にお電話ください
096-322-5222


お問い合わせは
お気軽にお電話ください
096-322-5222
西村芳弘 プロフィール
| 1970年 | 兵庫県明石市に生まれる。 |
| 1989年 | 広島県立海田高校を卒業する。 |
| 1996年 | 東京藝術大学工芸科陶芸専攻を卒業する。 |
| 1998年 | 同大学大学院陶芸専攻を修了する。 |
| 1998年 〜 | 広島県三次市・広島市にて作陶を開始する。 |
| 2002年 〜 | 尾道大学デザイン科非常勤講師を勤める。 |
| 2005年 | 日本陶芸展・長三賞現代陶芸展に入選する。 |
| 2006年 | 益子陶芸展・金子審査員特別賞を受賞する。 |
| 2007年 | 日本陶芸展に入選する。 |
| 2008年 | 「陶で彩る〜現代の造形」展に造形作品を出品する。(東広島市立美術館) |
ギャラリー青鞜(広島)・ギャラリー船岡(滋賀)・
ギャラリー栄光舎(鳥取)・EN陶REZ(神戸)・桃林堂・
ギャラリー上原・ギャラリーおかりや(東京)・
ギャラデー器館(京都)・ギャラリーラウラ(愛知)・
三良坂竹工房(広島)・ギャラリー邁(東京)・
ギャラリー山手(横浜)・広鳥三越・浦和伊勢丹・
新宿高島屋等
造形作家・西村芳弘さんからのメッセージ
人間とは山のような存在なのかもしれません。緩やかな丘のような山もあれば、険しく登ることが困難な山も・・。
又人が入りやすい山道、逆に峰が立ち行く手を拒むような険しい山道。
何だか人の心のようではないでしょうか?
そんな事を感じさせる存在になればと思っています。
■焼き物である事■
粘土は元々、地球上の岩石が色々な作用で粉砕・風化・蓄積したものです。
それを高温で焼き締めるという事は、ある意味岩石に戻す作業なのかもしれない。
だが再び粘土状に戻すのには10数万年といった気の遠くなる時間が必要です。
それに比べると焼き上げる時間のなんという短さでしょう!
高温(1200度以上)で焼成すると歪みや表面に亀裂などが生じる事もあるためか、伝統的人形や彫刻では低温(900°C前後)で焼かれるテラコッタとしている事が多いのですが、私は高温で焼成した時のあの質感が「ギユッ」となった高密度感が焼き物らしくて、また地球上の岩石を思い起こさせるので好きなのです。
山肌から露出した岩石を人がさすってしまう様に、手に対する抵抗、ザラザラ・ガサガサ等といった人から少し距離を置くような質感が多少あるほうが、手になじむのかもしれません。
わざわざ焼かなくてもいいような造形ではなく焼いた事による特徴・質感を作品の要素として生かしたいものです。
■土・技法■
私が住んでいるところは産地ではありませんが、幸いに広島では焼き物用の良質な粘土が産出されます
使用する粘土は広島産出の粘土と粘りや鉄分の調整用に若干の他地域(美濃や信楽等)の土、また自身で掘って来た粘土をブレンドしています。
製作のための技法はいろいろありますが、しいて上げると手やブラシなどで作品をこする事です。
素焼きを終えた後に溶化化粧(白化粧土を単体でも溶けるようにしたもの)を掛け、その後にこすりもう一度素焼きをするかそのまま粕薬を薄く掛け焼成します。
こすることで化粧土が剥がれ落ちて、地がのぞき新しいものなのに手ずれた古いもののようになります。
昔のフレスコ画・仏画や骨董品は時間の経過を経る事によってけばけばしさ等が無くなりなじんでゆきます。
また発掘されたりした物は何か凝縮しているのだけどもあまり嫌味ではありません。
単なる古ぼけた質感ではなく時間に耐え風化してそれでもそこに存在しているという存在、そんな物・状態に魅かれます。
そのような時間の経過や凝縮を表したくてこすり落とす技法を主にしています。
焼成は電気窯で、1250度・23時間ほどで行います。
作品によっては窯に入れるときに組み立ててしまう事があるので大変気を使います。
また「金・白金(プラチナ)彩」や「上絵・袖下顔料」などの技法を使って作品に様々な色合いを加えたり、「三彩」という唐や奈良時代からある袖薬の技法で、表現に幅を持だせようと研究しています。
■醸す■
制作はお酒造りと同じで自然や人間の手によるもの詩・音楽・埴輪・須恵器、陶傭、中東・アフリカの住宅・工芸等など気になるもの・興味をそそる物達が色々ありますが、それらが自分の中で発酵したものを醸し出し、人に楽しんでもらえばいいと思います。
詩人が言葉を醸すように、わたしは形を醸すのです。
■詩を謡う■
学生の時に詩の世界にはまり詩人にあこがれました。
詩人は世の中のあらゆる出来事・森羅万象を見て感じ、独自の言葉に訳します。
私は感じた事を言葉で謡うのではなく、やきもので謡いたいと思っています。
出来上がった形が私の言語だからです。
■器であること■
戯器というシリーズは、「鳥獣戯画」からきています。
いわゆる実用的な器とオブジエの中間の物を何か言い表す言葉として「鳥獣戯画」から引用した造語です。
獣や人が器と戯れたり、また私自身が土と戯れたりする結果としてできてゆく「カタチ」でもあります。
戯(ざ)れるという言葉には
(1)ふざける。じやれる。たわむれるという意味や、
(2)風情がある。趣がある。しゃれているといった意味があります。
そんな雰囲気が作品から醸し出せればよいなと思っています。
もっとも作品の形態としてはオブジエ(またはフィギュア)ですが、あくまでも器という何かしらの機能・形態になるよう意識しています。
持論ですが器という形態は空間を内と外に分け内空間を抱擁する形態なのでしょう。
そしてその内側には、飲食物が入ったり、花等を生けたりとする機能性が潜んでいる中が『空ろ』であるから器(うつわ)なのかもしれません。
私は作品をムクの塊から作るのではなく、手ひねり等で中を空洞にして作ります。
外側から圧縮した形ではなく内側から膨らむような形が好きです。
埴輪等も中が空洞です。(技術的な理由もありますが)あれらも同じような理由があるのかもしれません。
どのような作品でも、あくまでも『空ろ=器』であるからその形態や機能を生かしそれらから想像しうるものを離れてゆきたいです。
■傭・・人のカタチ・動物のカタチ■
一般的な器は静的なものが多いと思います。
ある種の抽象芸術なのでしょう。
静的(抽象的)な物ではなく動的な物(具象的)のほうが私の感じるイメージを表現しやすいのではと思い、人や動物のカタチを作っています。
人物などはある特定の人物ではなく、言葉や詩などから得たイメージの人物像です。
目を閉じさせている事が多いのですが、何か思うということが強調できればいいなと思い、その様な姿の代表格である仏像の「半眼」を意識しています。
動物の場合ただその姿を写すのではなく、又特別な動物等ではなくてありふれた家畜をモチーフに何かしら擬人化の要素(形がそのものであっても、顔が人のような表情)を加えています。
誠に単純なのですがキリスト教に『迷える子羊』という表現があります。
我々は常に迷いながら生きています。そしてまた人間も動物です。
動物を人間の形に当てはめる事でより人間というものが見えてこないかと思い、読書したり演奏したりと人間らしい行動をさせた羊等の『カタチ』を作るのです。
特別におりがたい様な姿のものでなく古代中国の「陶傭」の様なほほえましい姿でもありたいです。
神秘的なものではなく、そうではない物にも普遍性はあると思います。
そういった意味からも特別な姿・動物では無い『カタチ』動物や人の形を通して自然や人に営みの不思議さや詩的なものを表現できればと願い制作をしています。